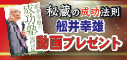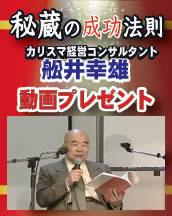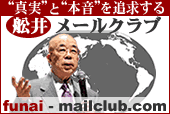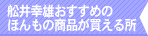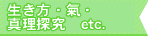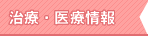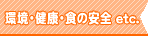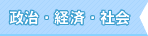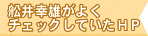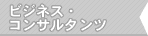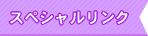トップが語る、「いま、伝えたいこと」
衆議院選挙で自民党が大勝しました。昭和の余韻を引きずっていた時代ですが、新聞記者の方から「解散と公定歩合については嘘を言ってもいい」ということを教えていただいたことがあります。事前に漏れると効果がなくなるので首相の専権事項である衆議院の解散と当時の日銀の公定歩合(いまなら金融政策決定会合で金利の上下を決めることに相当します)については記者に真意を問われても嘘を言ってもいいと許容されていたということです。今回の高市総理の解散はまさに寝耳に水で総理の作戦勝ちということになります。
市場は、高市政権をリスクの高い政権だと見ています。消費税減税を公約として堂々と掲げていますし、積極財政でマーケットが大事にする財政規律を重視していないことは明らかなので非常にリスクが高いと見ているようで、大勝の見込みが伝えられても一本調子で株価が上がっていくわけではありませんでした。ただ、長い目で見てみると右肩上がりの推移をしていて、やっぱり政権与党の勝利は買いだということになっているようにも感じられます。2週間前にも書きましたが、TINA(株式投資以外に選択肢はない)という状態にあるというのが金融市場の現状ですので、どうなっても株価は上がっていくように感じます。
ただ、すでに株で儲かっている方はそろそろ気を付けるべき段階に入ってきているようにも感じます。つまり、リスクはかなり大きくなっているのですが、まだ株を買えていない人は、勇気を持って株を買わなければいけないステージになったのだと感じています。投資ができる人とできない人の格差がものすごく大きくなっていく選択を私たちはこの選挙でしたことになります。いろいろな意見はあると思いますが、日本が国力を取り戻していくという面では豊かになっていける人から豊かになっていこうという選択は間違っていないと感じています。
リスクを取って勇気を持って投資をできるかどうかでここからしばらく豊かに暮らせるかどうかが決ってくるのだと感じます。インフレ傾向はまだまだ続き、円安で金利高、そして株価は大きな視点で見ると上がっていきます。給与収入だけで生活していく方は相対的にドンドン貧しくなっていきますし、何よりもデフレの時代に積み重ねた預貯金を頼りに生きていこうという人生設計の方にとっても厳しい時代がやってくることになります。楽しいことではありませんし、いいことだとも思いませんが、軍事費はますます増大して原発も動き始めます。半導体工場が日本に返ってきているのが象徴ですが、それによって国力は格差という犠牲を広げながら強くなっていくことになるのだと思います。
今週紹介させていただくのは、加来耕三著『豊臣秀長「補佐役」最強の流儀』(ビジネス社)です。大河ドラマ「豊臣兄弟」の影響もあり、秀吉の弟である秀長は現在注目度を高めています。この本のPRのためもあって「ザ・フナイ」の巻頭対談を加来先生とさせていただきました。何月号になるのかは未定ですが、楽しみにしていただければ思います。加来先生と対談させていただくのは2回目で3年前にちょうど大河ドラマの主人公が徳川家康だったときでした。ちょっと裏話ですが、NHKは紫式部と蔦屋重三郎を主人公にした大河をその間に放映したのですが、目的は合戦シーンがないので製作費が節約できたことにあったのではないかと教えてくれました。真偽はわかりませんが、ありそうな話に思えました。
秀吉は人気コンテンツですが弟の秀長はスポットライトが当たることは殆どなく、よく居る有名武将の親族、縁故で立場を得た側の人間として括られていたような印象さえ受ける彼がどうしてドラマの題材となったのか再評価されているのか、その部分について知ることができるのが本書になります。対談で盛り上がったのは、1985年に堺屋太一先生が出版された『豊臣秀長』(PHP文庫等)。この本以降、秀長が歴史の表舞台で取り上げられるようになったと感じています。これは名著なので加来先生の本と合わせてお読みいただければと思います。
加来先生は、秀長亡き後の秀吉の行動やそれに伴う結果、言ってしまえば失態の数々から、弟である彼が実はかなり重要な役割を担っていたと分析しています。政治、経済、芸能、スポーツなど、どこにでも言えることですが、優秀な側近を失った結果、落ち目となっていく事例は数多く耳にします。主役のみに目が向く時代は終わりを告げ、裏方にもスポットライトが当たる時代であるからこそ、補佐役の重要性は見直されており、秀長の事例を深く知ることは、それを再確認するために最適です。
加来先生の独自の視点、解釈を交えながら、秀吉が天下人になるまでの過程と、その傍で秀長がどのような役割を果たしてきたのが解説されていくのですが、歴史を辿っていくので、これは大河ドラマの予習的な役割も期待できます。武士となったきっかけからして、望んだものではないようですし、自らの意思でそこに入ったとも言い難いのかもしれません。紹介されている秀長の役割は裏方、言ってしまえば地味でもあり、損な役回りを常に担う立場から、兄や周囲に振り回される日々を羨ましがる方は少ないと思います。しかしだからこそ、それを担える人材は英雄の成功譚には絶対に必要で替えの利かない優秀な人材であり、個性的な兄の潤滑油や緩衝材的な存在として欠かせない存在であったことを理解できます。
補佐役に適性のある存在だけでは、何かを成しえるのは難しいかもしれない。しかし、優秀なリーダーでも単独では同様のことが言え、大きな成功のためにはどちらも必要な存在であり、相互に支え合ってこそであることを改めて教えてくれる一冊でした。安倍総理には菅官房長官や今井尚哉秘書官など強力な補佐役がいましたが、高市総理にもそのような方がいるのかどうかも気になるところです。令和だからこそ必要な補佐役の存在を改めて考えてみたいと思います。
=以上=
2026.02.02:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】衆議院選に思う (※佐野浩一執筆)
舩井 勝仁 (ふない かつひと)
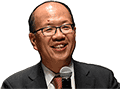 株式会社船井本社 代表取締役社長 株式会社船井本社 代表取締役社長1964年大阪府生まれ。1988年(株)船井総合研究所入社。1998年同社常務取締役 同社の金融部門やIT部門の子会社である船井キャピタル(株)、(株)船井情報システムズの代表取締役に就任し、コンサルティングの周辺分野の開拓に努める。 2008年「競争や策略やだましあいのない新しい社会を築く」という父・舩井幸雄の思いに共鳴し、(株)船井本社の社長に就任。「有意の人」の集合意識で「ミロクの世」を創る勉強会「にんげんクラブ」を中心に活動を続けた。(※「にんげんクラブ」の活動は2024年3月末に終了) 著書に『生き方の原理を変えよう』 |
佐野 浩一(さの こういち) 株式会社本物研究所 代表取締役会長 株式会社本物研究所 代表取締役会長公益財団法人舩井幸雄記念館 代表理事 ライフカラーカウンセラー認定協会 代表 1964年大阪府生まれ。関西学院大学法学部政治学科卒業後、英語教師として13年間、兵庫県の私立中高一貫校に奉職。2001年、(株)船井本社の前身である(株)船井事務所に入社し、(株)船井総合研究所に出向。舩井幸雄の直轄プロジェクトチームである会長特命室に配属。舩井幸雄がルール化した「人づくり法」の直伝を受け、人づくり研修「人財塾」として体系化し、その主幹を務め、各業界で活躍する人財を輩出した。 2003年4月、(株)本物研究所を設立、代表取締役社長に就任。商品、技術、生き方、人財育成における「本物」を研究開発し、広く啓蒙・普及活動を行う。また、2008年にはライフカラーカウンセラー認定協会を立ち上げ、2012年、(株)51 Dreams' Companyを設立し、学生向けに「人財塾」を再構成し、「幸学館カレッジ」を開校。館長をつとめる。2013年9月に(株)船井メディアの取締役社長CEOに就任した。 講演者としては、経営、人材育成、マーケティング、幸せ論、子育て、メンタルなど、多岐にわたる分野をカバーする。 著書に、『あなたにとって一番の幸せに気づく幸感力』 |