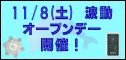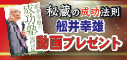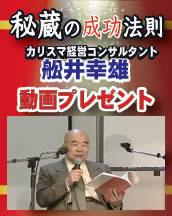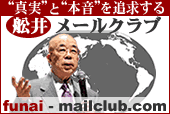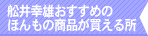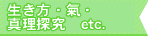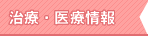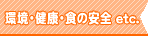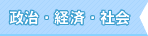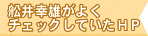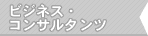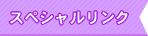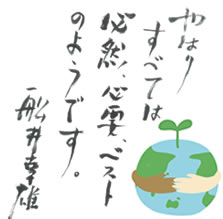
トップが語る、「いま、伝えたいこと」
イスラエルの旅から帰国しました。この旅行で得たものは大きく、日本に戻ってきて数日間、様々なことをかみ締めています。
まず、日本の四季折々に自然の変化が織り成す風土、そして日本人として遺伝子的に私たちに息づいている心のものさし、その両方の素晴らしさについてです。
日本には、砂漠はありません。狭い国土かも知れませんが、春には花が咲き、夏には鳥が鳴き、秋に豊穣の実りがあり、冬には自然の休息のように雪が降ります。イスラエルは国土の約60%が砂漠です。地中海の沿岸国としての地形には恵まれてはいますが過酷な風土であることは間違いありません。
イスラエルに滞在した10日間、いわゆる「パレスチナ問題」などのシビアな現実的現況を肌で感じ取る(感じ看る?)ことはできませんでした。
旅の半ばに行った「エリコ」の街は、キリストが洗礼を受けた町、約1万年前という遺跡としては人類最古の町として知られています。かつてはパレスチナ自治区にあるので、その治安状況が悪く、バスの運転手もユダヤ人からアラブ人に交代しないと町に入ることができませんでしたが、今回はそのようなことはありませんでしたし、切迫した緊張感は感じられず、穏やかな平和の風が漂っていました。
このたびの旅の目的は「聖書」を体感する旅でありましたが、この地を聖地と考えるキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の人々が熱心に祈りを捧げる姿には、ひたすら圧倒されました。これらの三つの宗教は唯一絶対神を信仰する『戦いの宗教』といっても過言ではないでしょう。神は預言者や人々に苦難を与え、人の方も神に反発しながら神から命じられたミッションを遂行してゆきます。預言者と呼ばれた人ですら、神の命に対して素直に従うのではなく、とてもそんなことは私にはできませんと逆らっていたということをガイドさんから教えてもらいました。
ユダヤ人は理屈が大好きな民だそうです。たとえ相手が神であろうと、その御使いの天使であろうと、自分の納得できないことははっきり言います。そして2000年ぶりにイスラエルを建国した時に最初にしたことが、ヘブライ語を復活させることでした。
パレスチナ人はアラビア語ですが、イスラエルに住むユダヤ人はヘブライ語です。ヘブライ語は、文字は旧約聖書とともに古い時代から現代まで受け継がれてきましたが、言葉の方はユダヤ人がローマ帝国によってパレスチナを追われて、世界各地に離散してからは、お祈りの時に使う言葉以外は廃れていました。実質的には人工的に新しい言葉を作ったことになりますが、それを見事に今使いこなしていることに、本当にびっくりしました。
2000年前の死海文書を発掘したクムランの遺跡や、それを展示してあるイスラエル博物館にも行ってきましたが、団長の赤塚さんが「イスラエルの凄いところは、その2000年前の文章を子供たちでも読めることです」とおっしゃっていたのが、とても印象的です。そのためイスラエルの子供たちは建国に至る歴史から、その神話まで原文で読むことができるのです。
それに比べて、私は日本の『古事記』を原文ではとても読めませんし、例えば、戦後に書かれた本でも、言い回しが今に比べると格段に難しいので読むのに苦労します。『古事記』は西暦712年(和銅5年)に編纂されて、大体1300年目になります。和銅といえば、「和同開珎」を思い出す方もいるでしょう。この時代は、日本の経済や文化のまさに原点をなす時代でした。しかしこうした日本での歴史上の重要事項としての『古事記』の存在を知らない日本人はいないでしょうが、一歩踏み込んで、その内容はというと、とたんにあやふやになります。
とくに戦後の教育をうけて育った日本人(私も含めて)は、この『古事記』ばかりか、『日本書紀』も含めて『日本の神話』は、ほとんど教えられていないのです。このたびの旅で、ことさらに感じたことは、建国の神話も含めて自国の歴史を十分に教育されなかった日本での戦後の教育についてです。
このことがどれ程に重要問題であるか、日本人にとって如何に「決定的な喪失」であるかが、日本国民の間で認識されていないことです。単に日本の「文化」ということではなく、日本という国や国民の依って立つ「原点」とも言える大切なものが、現代の日本人からすっぽり抜け落ちているのです。
言葉と文字を失おうとしている民族は、民族としてのアイデンティを保つことができなくなる危険があるのです。
『古事記』よりももっと前に使っていた古語を復活させて、それを日常語にしてしまったイスラエルが、いかに凄いことをやっているか、歴史を失った民族を復活させることは、どれほど大変なことか、ユダヤという民族の歴史上の実践至上主義の精神に心を奪われました。
『ヤマト』の心を失わないようにするには、実は簡単なことではありません。ユダヤの民の苦難の歴史を通じて、『ヤマト』の心をもう一度見直し、現にイスラエルが世界に発信しているように、日本人は国民自らの自覚と建国の歴史にさらなる自信と覚悟をもって、世界に発信し続けなければなりません。
ユダヤの民は、初代イスラエルの首相であるベングリオンが、砂漠の国土を克服することが、イスラエルが真の平和を勝ち取る碇石であると訴え、その後の国民的努力によって、人類始めての砂漠の緑化に成功しています。
日本とユダヤには共通項が多くあり、日本とユダヤは同じ先祖をもっているという話もあります。
父が生前このようなことも言っていました。『日本、ユダヤ同祖論のことは理解できないが、日本とユダヤの民は同じ魂を持っている、それが両極端に現われているだけである』と。
今回イスラエルを旅して、まだ自分の中でつかまえられるような、つかまえられないようなテーマです。常に「故きを温ねて新しきを知る」姿勢で、たゆまぬ勉強を生涯続けた父の言葉が胸に響きます。
=以上=
2014.04.21:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】言葉を失わない努力 (※舩井勝仁執筆)
2014.04.14:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】キリストを感じる旅 (※舩井勝仁執筆)
2014.04.07:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】失うことを怖がらない (※舩井勝仁執筆)
ライフカラーカウンセラー認定協会 代表
1964年大阪府生まれ。関西学院大学法学部政治学科卒業後、英語教師として13年間、兵庫県の私立中高一貫校に奉職。2001年、(株)船井本社の前身である(株)船井事務所に入社し、(株)船井総合研究所に出向。舩井幸雄の直轄プロジェクトチームである会長特命室に配属。舩井幸雄がルール化した「人づくり法」の直伝を受け、人づくり研修「人財塾」として体系化し、その主幹を務め、各業界で活躍する人財を輩出した。 2003年4月、(株)本物研究所を設立、代表取締役社長に就任。商品、技術、生き方、人財育成における「本物」を研究開発し、広く啓蒙・普及活動を行う。また、2008年にはライフカラーカウンセラー認定協会を立ち上げ、2012年、(株)51 Dreams' Companyを設立し、学生向けに「人財塾」を再構成し、「幸学館カレッジ」を開校。館長をつとめる。2013年9月に(株)船井メディアの取締役社長CEOに就任した。 講演者としては、経営、人材育成、マーケティング、幸せ論、子育て、メンタルなど、多岐にわたる分野をカバーする。
著書に、『あなたにとって一番の幸せに気づく幸感力』