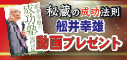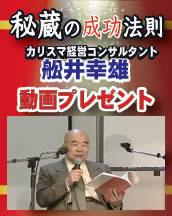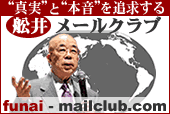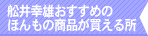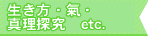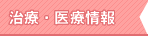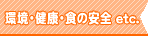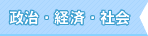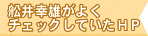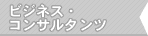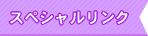トップが語る、「いま、伝えたいこと」
空海もはじめは迷っていた!
儒教か、道教か……、それとも仏教か?
空海が記したとされる『三教指帰』(さんごうしいき)の冒頭に「十韻の詩」というものがあります。高校生時代は漢文アレルギーだったし、絶対に足を踏む入れまいと思っていたのですが、踏み入れてしまいました……。
でも、あの空海ですら、文章に示し、残すほどに葛藤があって、仏門、密教の道に入ったと思うと、人間らしいなって思えたのです。『三教指帰』というのは、難解な書ということで有名ですが、もちろん私も解説書を参考にさせていただきました。
おもしろいと思ったので、少々お付き合いください。
嗟嗟浮生、若夢若驚。
芸芸兆品、誰其知情。
駕鴻凌紫、乗策朝明。
余光尚照、煙霧之城。
高栄赫奕、暫爾虚声。
假合為身、畢竟無形。
臥龍蔵曜、舞鳳含英。
照潭則影、應器則声。
名章上籍、徳配無名。
則知儒術、徒自矜名。
AIにその現代語訳をさせたところ、つぎのように書いてきました。
ああ、この浮き世の人生は、夢のように儚く、雷のように一瞬で過ぎ去る。
多くの人々が生きているが、誰が真に人生の意味を知っているのか。
高く飛ぶ鳥のように名声を追い、朝の光に向かって走るようなものだ。
それでも、その輝きはかすかで、煙のように消えてしまう都の栄華に過ぎない。
一時の栄光は、実は空虚な音に過ぎない。
肉体は仮に成り立っているが、結局は無に帰する。
才能ある人が光を秘め、徳ある者が花の香りを抱いているようでも、
それは水面に映る影のようであり、器に響く音のようなもの。
儒教の経典に名を記しても、徳は無名にとどまる。
だから私は思う――儒教の学問は、ただ虚名を誇っているに過ぎない、と。
空海はこの詩を通じて、
「人の命は短く、世の中の名声や富は幻にすぎない。
それらに執着することは虚しい。
真理に至るためには、儒教でも道教でもなく、
仏教の教えこそが唯一の道だ」
という自己の思想的決意を、詩的かつ批判的に示したものと考えられます。
ちなみに、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』というものもあって、これは『三教指帰』の草稿本と言われています。この2つが同一のものという説もあります。空海の処女作で、延暦16年(797年)、空海24歳の時に書かれた戯作形式の宗教比較論です。構成は、儒教の立場から道徳を説く「亀毛先生論」、道教の立場から不死の神仙術等を説く「虚亡隠士論」、儒教、道教に対して仏教がいかに優れているかを説く「仮名乞児論」(「無常の賦」、「生死海の賦」を含む)の三部から成ります。
『三教指帰』では「序文」が加えられ、「十韻の詩」が書き換えられ、さらに数箇所字句の添削がなされているそうです。『三教指帰』は、空海自身の心境変化を告白したもので、大学の業を捨て、ひたすら仏道に精進しようとの決心覚悟を示した出家宣言とみなすことができます。
空海は『三教指帰』の序章にこの書物を書いた理由を記しています。
「空が晴れ渡っているときには必ず太陽がそのおおもとに現れているように、人が心に何かを感じたときにこそ、人は筆を執って、その思うところを文章であらわすのです」と……。
このように、若き日の空海が、考えに考えて、儒教と道教と仏教はどれが一番優れているかについて答えを出したといいます。もちろん、全部素晴らしい教えであることは間違いないわけで、そういう視点で見ると、空海自らが儒教と道教と仏教を同時に解説してくれる書物という見方もできます。
仏教に傾倒した空海は、大学(貴族の子弟が通う学校)を中退し、求聞持法(ぐもんじほう)を極め、仏道修行をしようと決意します。『三教指帰』には当時の空海の気持ちが込められています。これから、それぞれのストーリーを見ていきたいと思います。
★第一幕:儒者先生との出会い〜「正しさ」は人を救うか?〜
旅の途中、仮名乞児は、立派な衣をまとい、どこか自信満々な儒者先生に出会います。
「人は仁義を守り、礼を尽くせば、立派な人生が送れるのだよ。孝行を尽くし、忠義を果たせば、それで十分だ」と語る先生。乞児はしばし感心します。なるほど、それもひとつの答えかもしれない。
「でも、人はいつか死にますよね。死んだら忠義も礼も関係ないんじゃ……?」
「悪人が栄えて、善人が苦しむこともあります。どうしてですか?」
核心を突く質問に、儒者先生の顔が曇ります。「……それは……えーと……まあ、運命というか……」
次第に歯切れが悪くなり、先生は退場。礼節や倫理は立派だけど、「死」と「苦しみ」への答えは、持っていなかったのです。
★第二幕:道士との対話〜「不老不死」は本当に救いか?〜
次に出会ったのは、煙のように現れた謎の道士。山中に住み、呼吸法と薬草で「仙人になる修行」をしているといいます。
「世の中の苦しみなんぞ、気にする必要はない。無為自然、風のように生きればいいのだ」
「努力次第で、人は老いも死も超えられる」
その言葉に、乞児の目が輝きます。「それなら、苦しみから逃れられるじゃないか!」
だが彼は問います……。
「もし千年生きても、苦しみが終わらないなら? 人が死んでいく意味を、どう説明しますか?」
「すべてを忘れて浮かんでいくだけの人生って、本当に意味がありますか?」
道士はうっすら笑いながら、霧のように姿を消します。
……答えは風の中。
長生きはできるかもしれない。でも、「なぜ生きるのか」「なぜ苦しむのか」には、触れられなかったのです。
★第三幕:沙門との対話〜「苦しみを超える道」はどこにある?〜
最後に現れたのは、静かで柔らかいまなざしを持つ沙門(仏僧)。
乞児が「人生の苦しみとは何か」「どうすれば救われるのか」と尋ねると、沙門はゆっくりと答えます。
「苦しみの原因は、執着にある。物事を『自分のもの』と思うことで、人は縛られる」
「万物は空(くう)であり、変化するものに永遠はない。だからこそ、執着から離れなさい」
「因果の理(カルマ)に従って、生死は繰り返されるが、悟りによってその輪廻から解き放たれる」
乞児は静かに涙を流します。
これまでのどの教えにもなかった、「生きる意味」と「死の向こう側」への明確な答え。慈悲と智慧に満ちた言葉が、心の奥に届きます。
やがて、乞児は決意します。
「この身を空しくして、衆生を救おう」
迷える青年は、仏道に入ることで、自らの人生の意味を見出したのです……。
というお話です。
この物語の主人公・仮名乞児は、まさに若き日の空海自身です。儒教・道教・仏教という3つの思想の中で、「仏教こそが人間の根本的な苦悩に対して真に向き合える教えだ」
と確信し、求道の旅を決意します。
そしてこの後、空海は真の仏道を求めて唐(中国)へ渡り、密教の教えを受け継ぐことになります。そうした点で、『三教指帰』は、その旅立ちの精神的な序章とも言える物語であるといえます。
ご興味を持っていただけたでしょうか?
空海も私たちと同じく、悩める若者時代を過ごしたことを知って、どんな偉大な人間であっても、同じ人なんだなって感じました。
感謝
2025.08.18:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】空海も悩める若者であった……件 (※佐野浩一執筆)
2025.08.11:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】ペットとAI (※舩井勝仁執筆)
2025.08.04:【いま 一番知らせたいこと 、言いたいこと】もしかして、『繊細さん(HSP)』かも? (※佐野浩一執筆)
舩井 勝仁 (ふない かつひと)
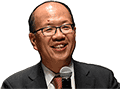 株式会社船井本社 代表取締役社長 株式会社船井本社 代表取締役社長1964年大阪府生まれ。1988年(株)船井総合研究所入社。1998年同社常務取締役 同社の金融部門やIT部門の子会社である船井キャピタル(株)、(株)船井情報システムズの代表取締役に就任し、コンサルティングの周辺分野の開拓に努める。 2008年「競争や策略やだましあいのない新しい社会を築く」という父・舩井幸雄の思いに共鳴し、(株)船井本社の社長に就任。「有意の人」の集合意識で「ミロクの世」を創る勉強会「にんげんクラブ」を中心に活動を続けた。(※「にんげんクラブ」の活動は2024年3月末に終了) 著書に『生き方の原理を変えよう』 |
佐野 浩一(さの こういち) 株式会社本物研究所 代表取締役会長 株式会社本物研究所 代表取締役会長公益財団法人舩井幸雄記念館 代表理事 ライフカラーカウンセラー認定協会 代表 1964年大阪府生まれ。関西学院大学法学部政治学科卒業後、英語教師として13年間、兵庫県の私立中高一貫校に奉職。2001年、(株)船井本社の前身である(株)船井事務所に入社し、(株)船井総合研究所に出向。舩井幸雄の直轄プロジェクトチームである会長特命室に配属。舩井幸雄がルール化した「人づくり法」の直伝を受け、人づくり研修「人財塾」として体系化し、その主幹を務め、各業界で活躍する人財を輩出した。 2003年4月、(株)本物研究所を設立、代表取締役社長に就任。商品、技術、生き方、人財育成における「本物」を研究開発し、広く啓蒙・普及活動を行う。また、2008年にはライフカラーカウンセラー認定協会を立ち上げ、2012年、(株)51 Dreams' Companyを設立し、学生向けに「人財塾」を再構成し、「幸学館カレッジ」を開校。館長をつとめる。2013年9月に(株)船井メディアの取締役社長CEOに就任した。 講演者としては、経営、人材育成、マーケティング、幸せ論、子育て、メンタルなど、多岐にわたる分野をカバーする。 著書に、『あなたにとって一番の幸せに気づく幸感力』 |